日本の夏祭りで人気のある金魚すくい。
金魚すくいといえば、紙製の「ぽい」を使って、破れないように何匹すくえるか。。。がですよね?
そんな金魚すくいで「もなか」を使う地域があるんだとか!
あの食べるモナカですよ!なぜにモナカなの?って疑問ですよね。
金魚すくいにモナカを使う理由を調べていくと「水」が重要なキーワードだったのです。
金魚すくいに「モナカ」を使うってマジ?
あけおめ。新年早々金魚すくい。
— Hirota (@mtkFE) December 31, 2024
SIGMA fp / Voigtlander NOKTON 35mm F1.4 pic.twitter.com/SYNpvpcTgA
金魚すくいと言えば、多くの人が紙の網を思い浮かべるでしょう。
しかし、驚くべきことに、モナカを使って金魚をすくう地域が実際に存在するのです。
「えっ、本当に?モナカって食べ物じゃないの?」
そう驚く人も多いはず。
実は、北海道の一部地域では、モナカを使った金魚すくいが伝統として残っているんです。
モナカは通常お椀型をしており、洗濯バサミや針金を取り付けて使用します。
「へー、面白そう!でも難しそうだなぁ」
確かに、紙の網よりも水に溶けやすいため、難易度は高くなります。
しかし、その分だけ挑戦しがいがあるとも言えるでしょう。
「モナカ、すぐ溶けちゃいそう。コツとかあるのかな?」
もちろん、コツはあります。
水につける時間を最小限に抑えることが重要です。
金魚が集まっている場所を狙い、水面に上がってきた金魚をモナカの縁でさっとすくい上げるのがポイントなんです。
金魚すくいがモナカの地域はどこ?
小学生の頃ミドリガメは「カメすくい」で金魚すくいみたいに屋台に出てたけどこれは地域性なのかそういう時代だったのか…??ちなみにもなかの皮ですくってた。当方下手すぎてすくえなかった。1回500円(たしか)→ pic.twitter.com/ByOPqzyo8L
— さとちあおち (@chiccaScolia) February 6, 2023
金魚すくいでモナカを使う地域として有名なのは、主に北海道の一部。
北海道の一部の地域では、この独特な方法が長年の伝統として受け継がれてきました。
テレビでよく見る金魚すくいはぜーんぶ紙のポイですよね。
一度も紙のポイで金魚すくいしたことないです(涙)
もう20年以上前の話ですから今は変わったのかもしれません。
ちなみに北海道数か所行きましたがすべてそうでした。
北海道限定??ほかの地域でもモナカポイのところあるのでしょうか?
でも札幌の大きいお祭りは紙のポイだった気もする…
引用:はてなブログ
しかし、全国的に見ると、モナカを使う地域はかなり限られているのが現状です。
「他の地域でもやってるところあるのかな?」
実は、熊本県の長洲町でも金魚すくいにモナカを使う文化が残っているそうです。
長洲町では、金魚すくいだけでなく、金魚をモチーフにしたお菓子も人気を集めているんだとか。
「へぇ、金魚づくしの町なんだ!行ってみたいなぁ」
確かに、ユニークな体験ができそうですね。
ただし、モナカを使う金魚すくいは、現在ではかなりレアな存在となっています。
ほとんどの地域では、紙の網、いわゆる「ポイ」を使用しているのが一般的です。
金魚すくいといえば、虫眼鏡のような形状の持ち手と丸く白い紙が貼られた「ポイ」を思い浮かべますよね?
モナカを使う地域が少ないのには、いくつかの理由があるんです。
「どんな理由なんだろう?気になる!」
それは、次の話題で詳しく見ていきましょう。
金魚すくいがモナカでポイではない理由!水分が秘密だった
モナカを使う金魚すくいが少ない理由、それは水分との関係にあります。
「水分?どういうこと?」
モナカは水に触れるとすぐにふやけてしまうという特性があるんです。
ポイと違って、モナカはボロボロになりやすく、水槽を汚してしまう可能性が高いのです。
「あー、なるほど。確かに水槽が汚れちゃうのは困るよね」
そうなんです。清潔な環境を保つのが難しいというのが、大きな理由の一つなんです。
一方、ポイは水に濡れてもボロボロにならないので、水槽を綺麗に保つことができます。
「じゃあ、ポイの方が衛生的ってこと?」
その通りです。衛生面を考えると、ポイの方が優れているんです。
また、モナカは水に溶けやすいため、すくう時間が限られてしまうという欠点もあります。
「確かに、すぐ溶けちゃったら楽しめないもんね」
ポイなら、ある程度の時間使えるので、子どもたちも十分に楽しむことができるんです。
「でも、モナカの方が難しそうだから、大人には面白いかも?」
難易度が高い分、挑戦しがいがあるかもしれませんね。
ただし、イベントとして考えると、ポイの方が運営しやすいという利点があります。
「なるほど。いろんな理由があるんだね」
そうなんです。でも、モナカを使う金魚すくいには、実は興味深い歴史的な背景があるんですよ。
金魚すくいでモナカを使うようになったのはいつ?
金魚すくいでモナカを使うようになったのは、実は江戸時代にまでさかのぼります。
「えっ、そんな昔から?」
そうなんです。
江戸時代には今のようなプラスティックと紙製のものはないありませんからね。
金魚が日本に広まったのは室町時代頃だと言われています。
当時、金魚は高級品で、一部の貴族の観賞用としてのみ存在していました。
「へぇ、金魚って昔は高級品だったんだ」
江戸時代になると、金魚の養殖が盛んになり、一般庶民にも手に入るようになりました。
そして、子どもたちの間で魚をすくう遊びが流行り始めたんです。
「そこから金魚すくいが始まったってこと?」
当初は紙を使っていましたが、紙が貴重だったため、代わりにモナカを使うようになったんです。
「なるほど!モナカなら食べられるし、一石二鳥だったんだね」
そうですね。モナカは水に溶けやすいので、すぐに破れてしまいます。
これが、金魚を持ち帰りにくくする工夫にもなっていたんです。
「へぇ、そんな理由があったんだ。面白い!」
明治時代になると、金魚の持ち帰りが可能になりました。
そこから、現在のような紙の「ポイ」が使われるようになったんです。
「じゃあ、モナカから紙に変わったってこと?」
大正時代にポイが登場すると、モナカを使う屋台は急激に減っていきました。
ですが、先ほど紹介した北海道や熊本の一部では今でもモナカを使う金魚すくいが残っています。
「歴史を感じるね。一度やってみたいなぁ」
確かに、貴重な体験になりそうですね。
金魚すくいの歴史を知ると、より深く楽しめそうですね!
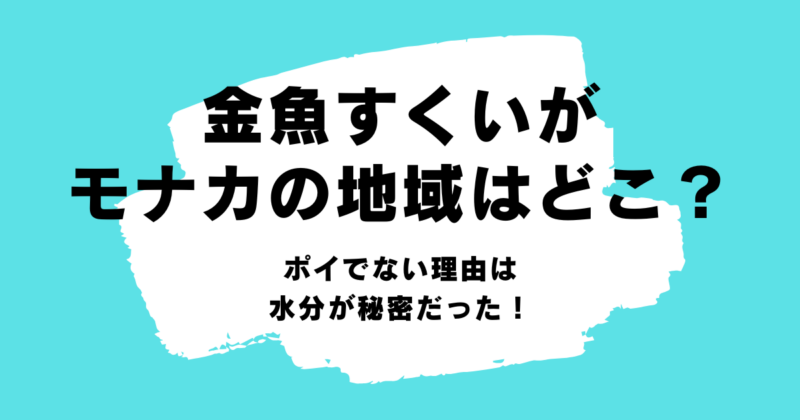
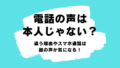
コメント